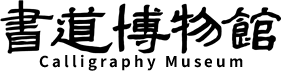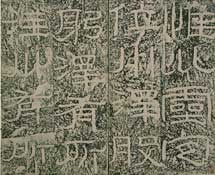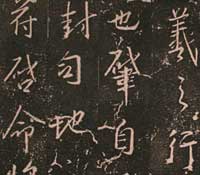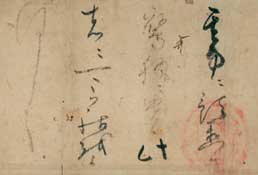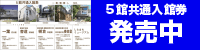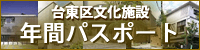| 台東区立書道博物館特別展 | 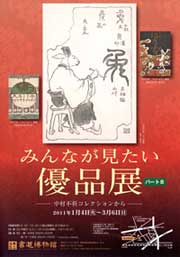 |
|---|---|
| 「みんなが見たい優品展 パート8」 展示一覧 | |
| 平成23年1月4日(火)〜3月6日(日) | |
| 昨年1年間、当館のアンケートでリクエストして頂いた作品を中心に展示しています。 | |
※文章、画像の転載は固く禁じます!
中村不折記念館
【1F 第1展示フロア-】
大型展示ケース
|
1:臨顔真卿裴将軍詩軸 中村不折(1866〜1943)筆/大正7年(1918) |
|---|
| 中村不折53歳の書。唐時代の大家・顔真卿の書として伝わる「裴将軍詩」を臨書し、健筆会展に出品した超大作。 |
|
2:行書四字「克己復礼」双幅 貫名菘翁(1778〜1863)筆/江戸・文久元年(1861) |
| “幕末の三筆"の1人・貫名菘翁の大作。“克己復礼"は、自分の欲を抑え、礼儀にかなった行動をとるという意味である。 |
【1F 第1展示フロア-】
展示ケース
|
3:石門頌(旧拓) 後漢・建和2年(148) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 不通となっていた褒斜道(現在の陝西省にあった要路の1つ)の修復に尽力した楊孟文の功績を刻んだ摩崖の拓本。 | ||||
|
4:韓仁銘(明拓) 後漢・熹平4年(175) |
||||
| 優れた政治を行ったが、若くして没した韓仁の業績を称えるため、彼の上役が建てさせた石碑の拓本。 | ||||
|
5:薦季直表 鍾繇(151〜230)筆/三国(魏)・黄初2年(221) |
||||
| 三国時代、魏国の重臣として活躍し、また書に優れたと伝えられている鍾繇の書。魏文帝に季直の過去の功績を述べ、再び取り立てるよう奉る内容である。これは原本を写して石や木に刻み、拓本をとって冊子に仕立てた法帖(刻本)である。 | ||||
|
6:蘭亭序 -潁井本- 王羲之(303?〜361?)筆/東晋・永和9年(353) |
||||
| 中国書法史上、“書聖"と仰がれる王羲之の代表作。王羲之が蘭亭(浙江省)で客人を招いて宴を催し、そこで詠まれた詩を集めて添えた序文の原稿である。真筆は存在しないが、法帖や摸写本によってその面影が伝えられている。この「蘭亭序」は、明時代に潁上という地の、ある井戸の底から出土した「蘭亭序 -潁井本-」を模刻したもの。 | ||||
|
7:黄庭経 -潁井本- 王羲之 筆/東晋・永和12年(356) |
||||
| 王羲之の書として伝わる楷書作品の1つで、長寿を保つ秘訣を説く道教の経典『黄庭経』を書写した作品。「蘭亭序 -潁井本-」の原石には、反対面に「黄庭経」が刻まれていたという。これはその「黄庭経 -潁井本-」を模刻したもの。 | ||||
|
8:興福寺断碑 王羲之 筆/ 唐・開元9年(721) |
||||
興福寺の僧・大雅が、王羲之の作品から字を集めて建てた石碑の拓本。明時代の出土時から上半分を失った断碑であるため「興福寺断碑」と呼ばれるが、名が“文"という人物の功績を称えた石碑である。
|
【2F 第2展示フロア-】
|
9:皇朝十二銭 飛鳥〜平安(8〜10世紀) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 古代日本において、律令制度の下に鋳造された銅銭の総称。「本朝十二銭」とも呼ばれる。 | ||||
|
10:「和同開珎」銭笵 飛鳥〜奈良(8世紀) |
||||
| 「皇朝十二銭」の1つ「和同開珎」の鋳型。山口県出土と伝えられている。 | ||||
|
11:大聖武(手鑑「古今翰聚」所収) 伝 聖武天皇(701〜756)筆/奈良(8世紀頃) |
||||
| 聖武天皇の御筆と伝えられる、『賢愚因縁経』が書写された3行分。字粒が大きいことから“大聖武"と呼ばれる。 | ||||
|
12:内膳司解申請公粮牒 奈良・天平17年(745) |
||||
| 内膳司(天皇の飲食物を調理、献上する役所)の役人たちが、日々の食料や物資を申請するために作成した書類。 | ||||
|
13:臨楽毅論(「鄰蘇園帖」所収) 光明皇后(701〜760)筆/奈良・天平16年(744) |
||||
| 王羲之「楽毅論」を光明皇后が臨書した作品。「鄰蘇園帖」は、明治時代の書家達に学書法を説き、多大な影響を与えた楊守敬が制作した集帖(時代・官職を問わず、歴代の名筆を集めて複製された法帖集)である。 | ||||
|
14:伊都内親王願文(「鄰蘇園帖」所収) 伝 橘逸勢(?〜842)筆/平安・天長10年(833) |
||||
| “三筆"の1人・橘逸勢の書として伝わる作品。桓武天皇の皇女・伊都内親王が読経料を寄進する旨を記した文書である。 | ||||
|
15:大般若経巻第八十一 伝 朝野魚養(奈良〜平安・8世紀頃)筆/奈良(8世紀頃) |
||||
| 奈良時代の書写と考えられている『大般若経』のうちの1巻。当時書に優れた朝野魚養の書として伝えられている。 | ||||
|
16:戸隠切 藤原定信(1088〜1154〜?)筆/平安(11〜12世紀) |
||||
| 平安時代後期の官人であり、書き役としても活躍した藤原定信の書。『妙法蓮華経』が書写された3行分の断簡である。 | ||||
|
17:空海請来目録 最澄(767〜822)筆/平安(9世紀) |
||||
| 天台宗の祖・最澄の書の法帖。空海が唐から持ち帰った経典や仏具などを記録した「請来目録」を写したものである。 | ||||
|
18:秋萩帖 伝 小野道風(894〜966)筆/平安(9〜10世紀頃) |
||||
| 平安時代の代表的な草仮名(草書体の仮名)作品の1つ。これは江戸時代に作られた法帖の1つである。 | ||||
|
19:古今和歌集巻第八 伝 紀貫之(?〜946) 筆/平安(11世紀頃) |
||||
| 現存最古の『古今和歌集』の写本「高野切本古今和歌集」の8巻目。伊藤左千夫が不折夫人に贈ったものである。 | ||||
|
20:朱印状 織田信長(1534〜1582)筆/戦国〜安土桃山(16世紀) |
||||
| 戦国〜安土桃山時代の武将・織田信長が沢与助という人物に宛てた書状。鷹狩りに使う鷹を返させるよう命じている。 | ||||
|
21:草書詩冊 北島雪山(1636〜1697)筆/江戸(17世紀) |
||||
| 江戸時代中期に広く流行した唐様(中国風の書)の祖・北島雪山の書。五言絶句4首を草書で書いた冊子本である。 | ||||
|
22:行書尺牘軸 荻生徂徠(1666〜1728)筆/江戸(17〜18世紀) |
||||
| 江戸時代中期の儒学者であり、書にも優れた荻生徂徠の手紙。墓碑制度に関する問いに答える内容である。 | ||||
|
23:楷書「茶歌」軸 巻菱湖(1777〜1843)筆/江戸(18〜19世紀) |
||||
| 貫名菘翁、市河米庵とともに“幕末の三筆"と称される江戸時代後期の書家・巻菱湖が、「茶歌」を楷書で書いた作品。 | ||||
|
24:書巻 良寛(1758〜1831)筆/江戸(18〜19世紀) |
||||
江戸時代後期の禅僧・良寛の書。和歌や書簡、そしてひらがなの音韻を書き付けた紙片をまとめた巻子本である。
|
【2F 特別展示室】
|
25:百万塔 奈良・宝亀元年(770) |
|---|
| 藤原仲麻呂の乱を平定した称徳天皇が、戦没者の供養と国家の平和を祈願して作らせた100万基の小塔の1つ。 |
|
26:百万塔陀羅尼経 奈良・宝亀元年(770) |
| 百万塔の中に納められた『陀羅尼経』。制作年代が確実な世界最古の印刷物として知られている。 |
|
27:心経 伝 空海(774〜835)筆/平安・弘仁12年(821) |
| 真言宗の祖であり、嵯峨天皇、橘逸勢とともに“三筆"と称される空海が書写したと伝えられている『般若心経』。 |
|
28:行書七言二句軸 徳川光圀(1628〜1700)筆/江戸(17世紀) |
| 水戸藩第2代藩主であり、日本の歴史書『大日本史』の編纂を主導した徳川光圀の行書作品。 |
|
29:篆書七言二句軸 高芙蓉(1722〜1784)筆/江戸(18世紀) |
| 中国の古印を深く学び、優れた篆刻作品を残して“印聖"と称される江戸時代中期の篆刻家・高芙蓉の篆書作品。 |
|
30:行書五字軸 井伊直弼(1815〜1860)筆/江戸(19世紀) |
| 彦根(滋賀県)藩主を経て大老(老中の上に位置する臨時職)を務めた井伊直弼の行書作品。 |
【2F 中村不折記念室】
企画展「みんなが見たい優品展 パート8」の会期中、中村不折記念室では、不折の作品とともに小説『坂の上の雲』の登場人物であり、不折と親交の深かった正岡子規、夏目漱石の作品も同時に展示しています。
|
子規居士尺牘 下(6通目) 正岡子規(1867〜1902)筆/明治31年(1898) |
|---|
| 正岡子規が不折に宛てた手紙。『ホトトギス』の挿絵を依頼し、100号を迎える際にはご馳走することなどを伝えている。 |
|
正岡子規筆俳句歌留多 正岡子規 筆/明治(19〜20世紀) |
| 子規が江戸〜明治時代に活躍した俳家による句を選んで書いたカルタ。 |
|
漱石居士書翰 下(2通目) 夏目漱石(1867〜1916)筆/明治39年(1906) |
| 夏目漱石が不折に宛てた手紙。自身の短編集『漾虚集』の挿絵として描かれた不折の作品を賞賛し、礼を述べている。 |
≪ 中村不折 作品 ≫
| 【 書 】 | 「君が代」軸/御製「遠山雪」軸/草書七言二句額 |
|---|---|
| 【 絵画 】 | 豊干寒山拾得図双幅/七福神嬉遊図/大黒天図軸/高砂初旭図軸 |
| 【 新聞挿絵 】 | 十二支帖 |
| 【 その他 】 | 装幀(『ホトトギス』)/年賀状/ 『不折画集 第一』挿絵(海内無双美男子不折山人自惚之像) |
ギャラリートーク(展示解説)
| 日時 | 平成23年 1月30日(日) |
|---|---|
| 第1回:10時〜 第2回:13時30分〜 | |
| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |
| 申込方法 |
官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし入館料は必要です。 |
| 申込先 |
〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |
| 締切 | 第1回・第2回:平成23年 1月19日(水)必着 |