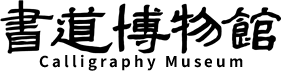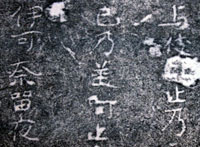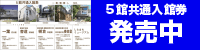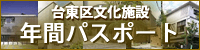| 台東区立書道博物館企画展 | 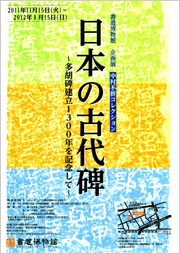 |
|---|---|
| 中村不折コレクション 「日本の古代碑 -多胡碑建立1300年を記念して-」 |
|
| 平成23年 11月15日(火)〜平成24年1月15日(日) | |
| 今年は、「多胡碑」が建立されて1300年目にあたります。本企画展は、中村不折コレクションの中から、「多胡碑」の拓本をはじめとする“上野三碑"、“日本三古碑"などの拓本を紹介するとともに、中村不折が『東京朝日新聞』に連載した新聞挿絵「上毛三古碑」も紹介いたします。また、参考資料として、石碑、摩崖などの起源がわかる中国古代の刻石資料の拓本も公開いたします。 | |
※文章、画像の転載は固く禁じます!
中村不折記念館
【1F 第1展示フロア-】
大型展示ケース
|
1:広開土王碑(第一面・第二面) 高句麗(414) |
|---|
|
2:広開土王碑(第三面・第四面) 高句麗(414) |
| 高句麗第19代の王、広開土王(生前は永楽太王と称した/在位391〜412)の功績を述べる「広開土王碑」の拓本。石碑の高さは6mを超え、東アジア最大級の大きさを誇る。1は整本、2は剪装本。どちらも石灰拓本である。 |
【1F 第1展示フロア-】
展示ケース
|
3:石鼓文(明拓) 戦国(前5〜前4世紀頃) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 石鼓と呼ばれる太鼓型の石に刻まれた、4言を基調とする韻文「石鼓文」の拓本。中国古代の著名な石刻資料である。 | ||||
|
4:泰山刻石 -十字本- 李斯(?〜前208)筆/秦(前219) |
||||
| 天下を統一した始皇帝が、視察で訪れた泰山(山東省)に建てさせた「泰山刻石」の拓本。書体は大篆(3「石鼓文」)をもとにして作られた小篆である。原石は方柱状の石であり、石碑の様式を備えたものではなかった。 | ||||
|
5:開通褒斜道刻石 後漢・永平9年(66) |
||||
| 褒斜道の修理・開通工事の完成を記念して刻まれた「開通褒斜道刻石」の拓本。天然の岩壁に刻まれた摩崖である。 | ||||
|
6:北海相景君碑(明拓) 後漢・漢安2年(143)頃 |
||||
| 北海国(山東省)の丞相(大臣)を務め、善政を行った景君の功績を述べる「北海相景君碑」の拓本。碑首(碑の上部。題を刻む部分を含む)、碑身(本文を刻む部分)、趺(台石)をそなえた、石碑の古い作例としても知られる。 | ||||
|
7:爨龍顔碑(旧拓) 劉宋・太明2年(458) |
||||
| 建寧(雲南省)の太守などを歴任した爨龍顔の功績を述べる「爨龍顔碑」の拓本。南朝の著名な石碑の1つ。 | ||||
|
8:鄭羲下碑 鄭道昭(?〜516)筆/北魏・永平4年(511) |
||||
| 北魏時代、太和年間を中心に活躍した鄭羲の功績を称えるため、雲峯山(山東省)中の岩壁に刻まれた「鄭羲下碑」の拓本。鄭羲の子、鄭道昭の書として伝わる。摩崖であるが、本文の上部に題字を頂く石碑の様式をとっている | ||||
|
9:張猛龍碑(明拓) 北魏・正光3年(522) |
||||
| 魯郡(山東省)において善政を行った張猛龍の功績を述べる「張猛龍碑」の拓本。北魏時代の楷書を代表する作品。 | ||||
|
【2F 第2展示フロア-】
|
10:龍蔵寺碑(明拓) 隋・開皇6年(586) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 恒州(河北省)を治めた、王孝僊が龍蔵寺を建てた経緯と、寺の荘厳な様子を述べる「龍蔵寺碑」の拓本。 | ||||
|
11:温彦博碑 欧陽詢(557〜641)筆/唐・貞観11年(637) |
||||
| 唐太宗に仕えた功臣、温彦博の功績を述べる「温彦博碑」の拓本。初唐の三大家の1人・欧陽詢81歳の書である。 | ||||
|
12:宇治橋断碑 飛鳥・大化2年(646) |
||||
| 僧の道登が宇治川に橋を架ける経緯を刻んだ「宇治橋断碑」の拓本。原碑は発見時当初から全体の3分の1のみを残す断片であった。京都府宇治市の橋寺放生院に現存している。重要文化財。日本の石碑としては現存最古の作例である。 | ||||
|
13:船王後墓誌銘 飛鳥(668) |
||||
| 推古、舒明天皇に仕えた船王後の墓誌の拓本。年月の明らかな墓誌としては日本最古のもの。原品は三井記念美術館蔵。国宝。薄い短冊状の銅板の表裏に銘文が刻まれている。 | ||||
|
14:金井沢碑 奈良・神亀3年(726) |
||||
| 上野国、群馬郡下賛郷の管理者の子孫たちが、遠い祖先および現世の父母の菩提のために建立した「金井沢碑」の拓本。「多胡碑」、「山ノ上碑」とともに“上野三碑"に数えられている。原碑は群馬県高崎市山名町に現存。特別史跡。 | ||||
|
15:東大寺大仏殿銅燈籠銘 奈良(8世紀) |
||||
| 上金銅八角燈籠(国宝)の火袋部分を支える柱(竿)に刻まれた銘文の拓本。燈籠は奈良、東大寺大仏殿の正面にある。 | ||||
|
16:仏足石歌碑 奈良(8世紀) |
||||
| 仏を称える21首の歌が上下2段に刻まれた「仏足石歌碑」の拓本。原碑は奈良県の薬師寺に納められている。国宝。 | ||||
|
17:仏足石銘 奈良(8世紀)/江戸・宝暦2年(1752) |
||||
| 奈良県の薬師寺に伝わる「仏足石」の銘と、側面に刻まれた銘文、そして「仏足石歌碑」の銘文を収録した版本。 | ||||
|
18:益田池碑銘 空海(774〜835)筆/平安・天長2年(825) |
||||
| 益田池は、かつて大和国高市郡(奈良県橿原市)に造られた貯水池である。この池の完成を記念して空海が筆を執り、「益田池碑銘」が建立された。原碑は現存しない。これは、高野山の釈迦文院に伝わる墨跡本を複製したものである。 | ||||
|
19:「多胡碑」(『集古十種稿』所収) 松平定信(1758〜1829)編/ |
||||
| 『集古十種』は、江戸時代の大名、社寺、諸家などに所蔵された古宝物の図録である。江戸時代後期に老中を務め、“寛政の改革"で知られる松平定信の編集である。ここに「多胡碑」などが収録されている。 | ||||
|
20:多賀城旧跡平瓦破片 年代不詳 |
||||
| 不折が昭和13年(1938)6月6日に多賀城址を訪れた際、「多賀城碑」の付近から見つけ出した瓦の破片。 | ||||
|
【2F 特別展示室】
≪第1期特別展示:10月9日(土)〜10月31日(日)≫
|
21:多胡碑 奈良・和銅4年(711) |
|---|
|
22:多胡碑 奈良・和銅4年(711) |
| 奈良時代の和銅4年3月9日、上野国(群馬県)内に多胡郡が置かれたことを述べる「多胡碑」の拓本。原碑は群馬県高崎市吉井町に現存し、特別史跡に指定されている。“上野三碑"の1つであり、“日本三古碑"の1つにも数えられる。 |
|
23:多胡碑(「耳比磨利帖」所収) 奈良・和銅4年(711) |
| 古代〜江戸時代の日本の名筆を集めて制作された集帖(書の名品集)である「耳比磨利帖」に収録された「多胡碑」。 |
|
24:上毛三古碑(「不折写景」所収) 中村不折(1866〜1943)画/ |
| 不折が日本各地の名所旧跡を訪ね、旅行記と挿絵を掲載する『東京朝日新聞』のシリーズ。夏目漱石の連載小説とともに同紙の目玉の1つであった。これは、後日不折が3冊分の帖に仕立てて保存したものである。今回は、不折が現地を訪れて取材した下絵も展示している。 |
【2F 中村不折記念室】
|
25:山ノ上碑 飛鳥(681) |
|---|
| 僧の長利が、母である黒売刀自のために建てた「山ノ上碑」の拓本。原碑は群馬県高崎市山名町神谷に現存しており、東隣にある山ノ上古墳とともに特別史跡に指定されている。“上野三碑"の1つ。 |
|
26:那須国造碑 飛鳥(700) |
| 文武天皇4年に国造(地方官)に任じられ、庚子の年(700)に没した那須直韋提の功績を称えた「那須国造碑」の拓本。現在は栃木県大田原市の笠石神社内の碑堂に現存する。“日本三古碑"の1つ。国宝。 |
|
27:多賀城碑 奈良・天平宝字6年(762) |
| 藤原朝臣朝(藤原仲麻呂の4男)が多賀城を改修したことを述べる「多賀城碑」の拓本。原碑は宮城県多賀城市市川の多賀城外郭南門跡に建てられた堂に現存している。“日本三古碑"の1つ。重要文化財。 |
| NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』第3部の放映に伴い、第2展示フロアーの一部および中村不折記念室では、正岡子規(1867〜1902)の書簡や、中村不折が描いた「日露役日本海海戦」に関する資料を展示しています。 |
|
(1)財神廟 中村不折 画/明治28年(1895) |
| 不折の水彩によるスケッチ。この時不折は子規とともに日清戦争の従軍記者として中国に渡ったが、すでに停戦となっていた。そこで不折は中国〜朝鮮半島の文化を見学し、スケッチしながら旅したという。これはその1枚である。 |
|
(2)大連湾柳樹屯 中村不折 画/明治28年(1895) |
| 従軍記者として子規と廻った大連(遼寧省)の様子を描いた水彩画。右から2隻目の船が、子規を乗せた海城丸である。 |
|
(3)子規居士尺牘 下 正岡子規 筆/ |
| 「子規居士尺牘」は、正岡子規が不折に宛てた手紙を不折自身が上、中、下の巻子に仕立てたものである。下巻5通目は、不折の画室新築の祝賀会の段取りについて。6通目は雑誌『ほととぎす』裏表紙の画を依頼している。 |
|
(4)俳句短冊 正岡子規 筆/明治32年(1899) |
| 明治32年、不折が画室を新築した際の祝賀会において、子規が自詠の俳句を書いた2種の短冊。 |
|
(5)葉書(在りし日の子規居士) 明治35年(1902)以後 |
| 子規の写真を用いて作られた葉書。この写真は明治32年(1899)6月19日に撮影された。 |
|
(6)『不折俳画』 中村不折 画/明治43年(1910) |
| 河東碧梧桐の俳句に不折が画を添えた俳画集。上下冊で40点を収める。下冊の末には子規が描かれている。 |
|
(7)子規居士十五週忌記念画帖 大正(20世紀)頃 |
| 子規の没後、不折や碧梧桐らによって出版された画帖。子規の絵は8枚収められている。 |
|
(8)白鳥先生碑 中村不折 筆/昭和2年(1927) |
| 幕末〜明治の教育者、書家であった白鳥拙庵を称えた石碑の拓本。少年時代の不折に書を指導した人物でもある。 |
|
(9)日本海海戦の資料 昭和(20世紀) |
| 不折が洋画作品「日露役日本海海戦」を描く際に用いた資料。取材した軍艦、三笠のスケッチや写真などがある。 |
|
(10)正岡子規像 中村不折 画/明治〜昭和(19〜20世紀) |
| 不折のデッサン。子規の横顔を鉛筆で描いている。 |
ギャラリートーク(展示解説)
| 日時 | 平成23年 12月11日(日) 10:00〜 / 13:30〜 (どちらかを希望のこと) |
|---|---|
| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |
| 申込方法 |
官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし入館料は必要です。 |
| 申込先 |
〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |
| 締切 | 平成23年 11月30日(水) 必着 |